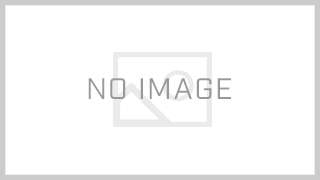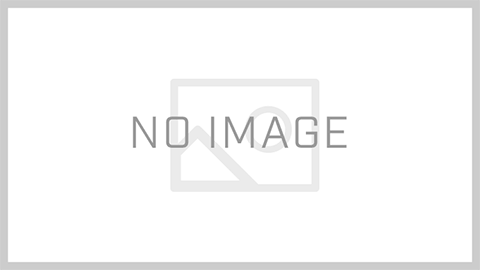大相撲の番付表で二番目に位置づけされている「大関」ですが、本当の意味を知っている方はあまりいらっしゃらないようですね。
もし、大関とはどんな意味ですか?と聞かれてもピンと来ない人が多いのではないでしょうか。
そこで、大関の意味や関脇から大関に昇進できる条件などを紹介して大関を深掘りしていきます。
大関の意味は「関取の第一人者!」
現代の大相撲では、大関は横綱の次に強いランク付けになっています。その昔、大関が最もランク付けの高い番付でした。
こちらの『大相撲・横綱の意味とは?昇進条件と過去の昇進成績をまとめてみた!』でも書いていますが、横綱は元々免許制度であって、強ければ誰でもなれるわけではありませんでした。
大関とは、関取の「関」に褒め称える意味を込めた「大」を付けて、大関となっています。
今でこそ横綱の地位が高いものになってしまったため、大関は最強クラスの力士ではなくなりました。横綱同様に、大関へ昇進するには一定以上の成績を収めなければ昇進出来ないので最強に近い力士と言えます。
千秋楽には、「これより三役揃い踏み」というアナウンスとともに、大関、関脇、小結が土俵に上がります。
そして、大関は横綱を除いた中で最高位となり、敢闘賞・技能賞・殊勲賞の三賞受賞対象からは外されています。
また、三役クラスが横綱から勝ち星を上げても金星にはなりませんので、大関も対象外となります。
関脇から大関への昇進条件と陥落条件とは?
相撲協会では関脇から大関への昇進条件として「3場所連続で関脇または小結の地位にあり、通算勝ち星が33勝以上」であることとされてます。
しかし、33勝に満たない力士であっても相撲内容や優勝力士との勝ち星差などによって、32勝でも大関に昇進した力士は過去に存在しています。
1990年以降では、25人の力士が大関へ昇進を果たしていますが33勝未満で昇進した力士は、「千代大海」「稀勢の里」「豪栄道」の3力士のみで、いずれも3場所の通算勝ち星が32勝でした。
優勝…赤色
同点優勝…水色
準優勝…黄緑色
| 四股名 | 3場所前 | 2場所前 | 1場所前 | 3場所合計勝敗 | 幕内優勝回数 | 最高位 | 大関在位 | |
| 1990年5月場所 | 霧島 | 小結・10勝5敗 | 小結・11勝4敗 | 関脇・13勝2敗 | 34勝11敗 | 1回 | 東大関 | 16場所 |
| 1992年7月場所 | 曙 | 小結・13勝2敗 | 関脇・8勝7敗 | 関脇・13勝2敗 | 34勝11敗 | 11回 | 64代横綱 | 4場所 |
| 1993年3月場所 | 貴ノ花 | 小結・14勝1敗 | 関脇・10勝5敗 | 関脇・11勝4敗 | 35勝10敗 | 22回 | 65代横綱 | 11場所 |
| 1993年9月場所 | 若ノ花 | 小結・14勝1敗◎ | 関脇・10勝5敗 | 関脇・13勝2敗 | 37勝8敗 | 5回 | 66代横綱 | 29場所 |
| 1994年3月場所 | 貴ノ浪 | 関脇・10勝5敗 | 関脇・12勝3敗 | 関脇・13勝2敗 | 35勝10敗 | 2回 | 東大関 | 37場所 |
| 1994年3月場所 | 武蔵丸 | 関脇・8勝7敗 | 関脇・13勝2敗 | 関脇・12勝3敗 | 33勝12敗 | 12回 | 67代横綱 | 32場所 |
| 1999年3月場所 | 千代大海 | 関脇・9勝6敗 | 関脇・10勝5敗 | 関脇・13勝2敗◎ | 32勝13敗 | 3回 | 東大関 | 65場所 |
| 1999年9月場所 | 出島 | 小結・9勝6敗 | 関脇・11勝4敗 | 関脇・13勝2敗◎ | 33勝12敗 | 1回 | 東大関 | 12場所 |
| 2000年5月場所 | 武双山 | 小結・10勝5敗 | 関脇・13勝2敗◎ | 関脇・12勝3敗 | 35勝10敗 | 1回 | 東大関 | 27場所 |
| 2000年7月場所 | 雅山 | 小結・12勝3敗 | 関脇・11勝4敗 | 関脇・11勝4敗 | 34勝11敗 | 0回 | 西大関 | 8場所 |
| 2000年9月場所 | 魁皇 | 小結・8勝7敗 | 小結・14勝1敗◎ | 関脇・11勝4敗 | 33勝12敗 | 5回 | 東大関 | 65場所 |
| 2002年1月場所 | 栃東 | 関脇・10勝5敗 | 関脇・12勝3敗 | 関脇・12勝3敗 | 34勝11敗 | 3回 | 東大関 | 30場所 |
| 2002年9月場所 | 朝青龍 | 関脇・11勝4敗 | 関脇・11勝4敗 | 関脇・12勝3敗 | 34勝11敗 | 25回 | 68代横綱 | 3場所 |
| 2006年1月場所 | 琴欧州 | 小結・12勝3敗 | 関脇・13勝2敗 | 関脇・11勝4敗 | 36勝9敗 | 1回 | 東大関 | 47場所 |
| 2006年5月場所 | 白鵬 | 小結・9勝6敗 | 関脇・13勝2敗 | 関脇・13勝2敗 | 35勝10敗 | 41回 | 69代横綱 | 7場所 |
| 2007年9月場所 | 琴光喜 | 関脇・10勝5敗 | 関脇・12勝3敗 | 関脇・13勝2敗 | 35勝10敗 | 1回 | 東大関 | 17場所 |
| 2009年1月場所 | 日馬富士 | 関脇・10勝5敗 | 関脇・12勝3敗 | 関脇・13勝2敗 | 35勝10敗 | 9回 | 70代横綱 | 22場所 |
| 2010年5月場所 | 把瑠都 | 関脇・9勝6敗 | 関脇・12勝3敗 | 関脇・14勝1敗 | 35勝10敗 | 1回 | 東大関 | 15場所 |
| 2011年11月場所 | 琴奨菊 | 関脇・10勝5敗 | 関脇・11勝4敗 | 関脇・12勝3敗 | 33勝12敗 | 1回 | 東大関 | 32場所 |
| 2012年1月場所 | 稀勢の里 | 関脇・10勝5敗 | 関脇・12勝3敗 | 関脇・10勝5敗 | 32勝13敗 | 2回 | 72代横綱 | 31場所 |
| 2012年5月場所 | 鶴竜 | 関脇・10勝5敗 | 関脇・10勝5敗 | 関脇・13勝2敗 | 33勝12敗 | 5回 | 71代横綱 | 12場所 |
| 2014年9月場所 | 豪栄道 | 関脇・12勝3敗 | 関脇・8勝7敗 | 関脇・12勝3敗 | 32勝13敗 | 1回 | 東大関 | 25場所 |
| 2015年7月場所 | 照ノ富士 | 前頭2枚目・8勝7敗 | 関脇・13勝2敗 | 関脇・12勝3敗◎ | 33勝12敗 | 1回 | 東大関 | 14場所 |
| 2017年7月場所 | 高安 | 小結・11勝4敗 | 関脇・12勝3敗 | 関脇・11勝4敗 | 34勝11敗 | 0回 | 東大関 | 8場所 |
| 2018年7月場所 | 栃ノ心 | 前頭3枚目・14勝1敗 | 関脇・10勝5敗 | 関脇・13勝2敗 | 37勝8敗 | 1回 | 西大関 | 2場所 |
※豪栄道、高安、栃ノ心の大関在位場所数は2018年9月場所までの数字
また、「照ノ富士」「栃ノ心」の2力士はいずれも3場所前の番付が、前頭であり平幕だった珍しいケースです。基本的には3場所前は小結以上が条件となっていますので、基準外とも言えますね。
そして、横綱と違って大関は関脇以下に降格することがあります!!
降格条件は「2場所連続で負け越し」となりますが、次の場所で10勝以上を上げれば大関へ復帰することが出来る特権も持ち合わせています。
極端な話、2場所連続大きく負け越したとしても、次の場所で10勝できれば大関へ返り咲けるという訳です。
また、大関として負け越し次場所を迎えた際には、「カド番」と言って瀬戸際状態となりプレッシャーのかかる場所を迎えることになります。
横綱は降格しない特権がある反面、成績が奮わなければ「引退」の二文字が常に付きまといます。一方で大関は降格する反面、負け越してカド番を迎えても猶予が与えられています。
大関から横綱に昇進するには、狭き門となっていますので大関に長く在位すればするだけ、カド番回数も増えるというわけです。
以下の表は、大関に在位しカド番を多く経験した力士になります。
横綱に昇進した力士はいませんので、大関に昇進してからモタモタしていると横綱にあがるのは難しいということになってしまいます。
| 順位 | 四股名 | 角番 | 大関在位数 | 大関に在位していた期間 |
| 1位 | 千代大海 | 14回 | 65場所 | 1999年3月場所-2009年11月場所 |
| 2位 | 魁皇 | 13回 | 65場所 | 2000年9月場所-2011年7月場所 |
| 3位 | 栃東 | 8回 | 30場所 | 2002年11月場所-2004年5月場所 2004年9月場所-2004年11月場所 2005年3月場所-2007年3月場所 |
| 4位 | 小錦 | 7回 | 39場所 | 1987年7月場所-1993年11月場所 |
| 琴欧洲 | 47場所 | 2006年1月場所-2013年11月場所 | ||
| 琴奨菊 | 32場所 | 2011年11月場所-2017年1月場所 | ||
| 豪栄道 | 25場所 | 2014年9月場所- | ||
| 7位 | 武双山 | 6回 | 27場所 | 2000年5月場所-2000年7月場所 |